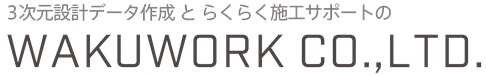ICT施工の始め方|部分ICT施工で段階的にチャレンジ
「ICT施工、やってみたいけど何から始めればいいのかわからない…」
県発注などの少し大きめの現場をやっている建設業仲間から、たまに聞くセリフです。
国土交通省が推進するICT施工は もはや「やるかやらないか」ではなく
「いつ始めるか」のフェーズに入っていますが、いざ始めようとすると、
「全面的にやらなきゃいけないの?」
「機材も人も足りないのに無理では?」と、
不安が先に立ちますよね。
実は、ICT施工は「全部を一気にやる」必要はありません。
測量や丁張といった、限られた工程だけにICT技術を取り入れる「部分ICT施工」という選択肢があります。
この記事では、ICT施工を「何から始めればいいか分からない」という方に向けて、部分ICT施工の具体的な始め方を、実践的に解説します。
この記事の要点(3行でわかります)
- 部分ICT施工(らくらく施工)なら、測量・丁張だけでも始められる
- 杭ナビ・快測ナビの使い方、初回チェックリスト、トラブル対処法を実践的に解説
- データ作成は外部委託でOK、徐々に自立してフルICT施工へステップアップ
お急ぎの方へ:読む場所を選べます
- 部分ICT施工について知りたい←全面ICTとの違いを理解
- 側溝工事での工程別解説を確認したい← 実際の使い方を工程ごとに理解
- よくあるトラブル対処法を確認したい ← データ表示、位置ズレ、バッテリー切れへの対応
- 2現場目以降の展開方法について知りたい ← データ外注しながら自立、フルICTへの道筋
まずは小さく
「ICT施工=全面ICT」じゃなくていい
全面ICTと部分ICT、どう違う?
ICT施工と聞くと、「3次元測量から設計、施工、検査まで全部ICT化する」という
全面ICT施工をイメージする方が多いかもしれません。
確かに、国土交通省が基準類を整備し、対象工種を拡大しているのは、この全面ICT施工です。
一方で、部分ICT施工は、工事のすべてではなく「一部の工程だけ」にICT技術を導入する方法です。
例えば、測量だけ、丁張だけ、出来形管理だけ、といった形で、できるところから始められます。
※全面ICT施工と部分ICT施工の違いについて詳しくは、「ICT施工とは?」もご覧ください。
中小現場なら「部分ICT」から始めるのが現実的
中小規模の土木会社にとって、いきなり全面ICT施工を導入するのは、正直ハードルが高いですよね。
人員も限られていますし、機材への投資も簡単ではありません。
だからこそ、まずは「部分ICT施工」から始めるのが現実的です。
測量や丁張といった、日々の現場で「時間がかかるな」「人手が要るな」と感じている工程から変えていく。
それだけでも、現場の負担は確実に減ります。
※丁張や測量の課題から考えたい方は、[丁張・測量の負担を減らす「らくらく施工」とは]もご覧ください。
部分ICT施工の”最初の一歩”、らくらく施工とは
らくらく施工の定義:杭ナビ・快測ナビで測量・丁張を変える
部分ICT施工の中でも特に始めやすい手法が、杭ナビ・快測ナビを使った「らくらく施工」です。
らくらく施工とは、「杭ナビ」や「快測ナビ」といったICT機材を使って、
測量・丁張・位置出しを効率化する施工手法のことです。
従来であれば、測量して、図面を見ながら丁張をかけて、位置を出して…という作業に多くの時間と人手がかかっていました。
らくらく施工では、この工程をICT機材に任せることで、「人が少なくても、正確に、早くできる」現場を実現します。
従来施工の延長だから、現場が混乱しない
らくらく施工のもう一つの特徴は、従来の施工の流れをガラッと変えるわけではないという点です。
測量して、位置を出して、施工する。この基本的な流れは変わりません。
変わるのは、「丁張をかける代わりに杭ナビで位置を確認する」「測量機を快測ナビで自動追尾させる」といった、道具と手順の一部だけです。
だから、現場の職人さんも「何やってるか分からん…」とならずに、スムーズに受け入れやすいんです。
杭ナビ・快測ナビの役割
- 杭ナビ:「測る・位置を出す」担当。2人作業が1人で完結。
- 快測ナビ:「見る・記録する」担当。設計データを可視化し、リアルタイムで出来形確認。
この2つを組み合わせることで、丁張や測量の負担を大きく減らすことが可能です。
▸らくらく施工の詳しい記述は[丁張・測量の負担を減らす「らくらく施工」とは]をご覧ください。
次の一歩
さらに、一歩進んだ部分ICT施工
はじめてICTに触れるときのオススメは、杭ナビ/快測ナビ の、「らくらく施工」でした。
丁張を最小にし、タブレットの色分け表示で「高い/低い」をその場で直す。それだけで手戻りは目に見えて減ったはずです。
そんな「らくらく施工」に慣れてきたら、もう少しだけICT要素を足せる選択肢があります。
たとえば、短い点群スキャンで地面のムラや障害物を先に把握しておく。
あるいは、MG(マシンガイダンス)でバックホウの整形を±20mmの範囲に収める。
どちらも“やり過ぎない”範囲で足すと、作業の迷いがすっと減り、段取りが静かに整っていきます。
黄色:この記述合っていますか?(沖村)
例:L型側溝据付(延長50m)を例に、“らくらく施工”の次の一歩
工事規模や体制に合わせて、いろんなパターンの部分ICTを実施。
工事について
対象
片側歩道・路肩でのL型側溝入替 又は 新設(曲線なし、直線50m想定)
出来形の判定面
底版天端・据付中心位置・据付高
狙う効果
- 位置出しの省人化(丁張最小)
- 据付高のバラつき抑制(色分け確認でその場是正)
- 出来形書類の短時間化(点群→断面・数量の自動化補助)0分)
構成要素
データ
- 軽量3D:中心線(CL)+勾配で作る簡易面(底版天端の基準面)
- 2D図(支給):L型の標準断面(寸法)
- 点群:既設の現況スキャン(短区間)
- (任意)正式3D:LandXML/TIN(数量・干渉が必要なら)
機材
- 杭ナビ/快測ナビ(位置出し・出来形色分け)
- レーザースキャナ(ハンディ or 地上型:短距離・屋外対応)
- MG(バックホウのバケット先端位置誘導:据付床の整形)
人員
- 運用担当1名(器械・データ)+OJT1名(据付班と連携)
※もし、初めてのICTの場合、現場をサポートしてくれる詳しい人がいると安心
全体フロー(2〜3日モデル)
Day 0:準備(社内)
最初に決めるのは、どの面で出来形を判定するか、と 許容差。
「今回は底版天端、許容差は±10〜15mmでいきましょう」。
これを紙1枚に書いて、発注者・監督・施工班の見方をそろえます。
3次元設計データは簡易なもので構いません。中心線(CL)と勾配から、底版天端の簡易な面をつくる。
MGを使うなら、その面を重機に渡して、“どこまで掘ればよいか”の目安にします。
整理
- 前提合意:出来形の“見る面”(底版天端)と許容差(例:±10〜15mm)
- 軽量3D作成:CL・勾配・起終点Zから簡易面を作る(正式3Dが不要ならこれでOK)
- MG用データ:整形床の高さ基準をMGに渡す(バケット先端誘導)
Day 1:測量・下準備(現地)
現場ではまず、既知点で座標と高さを合わせます。ここはいつも通りでOKです。
そのあとに、短い点群スキャンを一度だけ行います。
50mの範囲にさっとレーザーを走らせると、路肩の小さな段差や撓みが浮かび上がります。
重機を動かし始めたら、MGの誘導は±20mmで止めるのがコツです。
仕上げはタブレットの色分けで人が判断して、その場で直す→もう一度見る。
日が暮れる前に、このループを1回回しておくと、2日目が静かに始まります。
整理
- 基準点確認:既知点で座標系・高さ系を合わせる
- 点群スキャン(短区間):既設路肩〜側溝ラインを50m
- ねらい:現況の高低差ムラ・障害物の把握
ただし、点群が作業として重ければ、据付後のスキャンのみでも効果あり。
- ねらい:現況の高低差ムラ・障害物の把握
- MG試運転:基準面に対する整形床の掘削ガイド(±20mmで止める)
- 色分け照合:簡易面に対する現在面の高低をタブレット表示
- → 高い/低いをその場是正→再測(毎日1回はループ)
Day 2:据付(本作業)
中心線の位置出しは、杭ナビで軽やかに。
丁張を全面的に張らなくても、杭と画面があれば迷いません。
整形が済んだ床に側溝を据えたら、底版天端を色分けで確認。
「ここはあと5mm」「ここはOK」——同じ画面を見ながら、チーム全員の足並みが揃います。
最後にショートスキャンで出来形をひと撫で。
断面の記録や写真の付き合わせが、机に戻ってから楽になります。
整理
- 位置出し:杭ナビで側溝中心・据付ラインを誘導(丁張最小)
- MG誘導で整形完了:据付床の“面”を合わせる
- 据付→色分け確認:底版天端の高低を**±10〜15mm**で管理
- 出来形確定スキャン(ショート):据付後の出来形点群を取得
- 断面自動化・写真記録短縮に活用
オレンジ:全体的に違和感や間違いはありませんか?(沖村)
“どこまでICT化するか”は現場の都合でいい
全部ICTにする必要はありません。
位置出し+色分けで「回る形」を作る。そこに、点群やMGを要所に足すだけ。
この“足し算”は、現場ごとに決めて構いません。
- 「今回はMGなし、据付後だけスキャン」
- 「点群は事前に、出来形は写真中心で」
- 「色分けだけで十分。次の現場でMGを試そう」
どれも正解です。段階的に適合させていくことが、いちばんの近道です。
よくある不安やこの先について、まとめ
躓きポイント と 乗り越え方
- 判定面がふわっとしている
→ 着手前に面と許容差を紙で合意。これだけで現場の迷いが消えます。 - 点群が重すぎる
→ 範囲を50mに、解像度は用途に十分な下限に。 - MGが“効きすぎる”
→ 整形は±20mmで止め、仕上げは色分けで人が判断。 - 人によってやり方が違う
→ 命名・配布ログ・座標合わせをA4一枚の手順に固定。 - 最初から広げすぎる
→ 小区間×短期間で“型”を先に作り、次に広げる。
もし工種や規模を変えるなら
- 舗装の打替え100mなら、
点群(短区間)+色分けだけでも体感できます。 - 乗入れを含む側溝30mなら、
位置出しだけICT化して、据付はレベル管理×色分けで十分。 - 法面の軽微整形80mは、
MGでのICT建機施工がおすすめ!——出来形のスキャンは最後の一回でも構いません。
ピンク:全体的に違和感や間違いはありませんか?(沖村)
この先、どう展開していく?
操作は自社で、データ作成は外部委託という分業
1現場を終えると、杭ナビ・快測ナビの操作には慣れてきます。
だからといって、「2現場目から全部自分たちで」とはならないケースが多いかと思います。
実際によくあるのは、2現場目以降は、杭ナビ・快測ナビの操作は自分たちでやるけれど、
3次元設計データの作成は引き続き外部に依頼するというパターンです。
データ作成には専用ソフトや知識が必要ですし、外部に任せることで、現場は施工に集中できます。
これは「自立できていない」わけではなく、むしろ効率的な役割分担だと言えます。
規模の大きい工事では、フルICT施工へのステップアップ
何現場か経験を重ねていくうちに、
「次は規模の大きい工事でフルICT施工に挑戦してみよう」
というモチベーションが自然と生まれてきます。
らくらく施工を経て、次の部分ICT施工にも慣れておけば、
フルICT施工へのステップアップもスムーズです。
現場が慣れてきたら、他の工種にも展開
側溝工事で成功したら、次は擁壁工事、U字溝敷設、舗装工事など、他の工種にも展開していきましょう。
杭ナビ・快測ナビをはじめとしたICT機器は、
様々な工種で使えます。
一度使い方を覚えれば、応用が効くはずです。
まとめ
「やってみようかな」が、最初の一歩
部分ICT施工は、誰でも始められます。
杭ナビ・快測ナビを使うことで、測量・丁張・位置出しの負担を減らし、人が少なくても正確に早くできる現場を作れます。
大切なのは、「完璧にやらなきゃ」と思わないこと。
最初は伴走してもらいながら始めて、徐々に慣れていけばいい。
データ作成は外部に任せて、現場は施工に集中する。それで十分です。
そして、何現場か経験を重ねていけば、「次はもっと大きい工事でフルICT施工に挑戦してみよう」という道も自然と見えてきます。
「やってみようかな」と思ったら、それが最初の一歩です。
無料相談・現場見学会のご案内
部分ICT施工に興味を持たれた方、
「うちの現場でも使えるかな?」と気になった方は、
ぜひお気軽にご相談ください。
現場の状況をお聞きしながら、最適な始め方をご提案します。
関連記事
- 前の記事(丁張・測量の負担を減らす「らくらく施工」とは)
- 次の記事(【初めてのICT】ICT施工を成功させる“土台チェック”)
- サービスについて見る(ICT施工サポート)