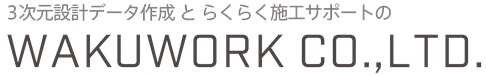丁張・測量の負担を減らす「らくらく施工」とは
「社長、丁張がしんどくて…」
現場からそんな声、出ていませんか?
人が足りない、ベテランに頼りきり、若手がなかなか育たない。
丁張や測量といった「当たり前の作業」が、いつの間にか現場の大きな負担になっている。そんな状況に、心当たりはないでしょうか。
人手不足が深刻化する中、丁張や測量に時間と人員を取られると、工期にも人件費にも影響が出ます。
かといって、「ICT施工が良いらしい。」と言われても、
何から始めればいいのか分からない。
そもそも、うちみたいな小さい会社でできるのか…?
実は、そんな悩みを抱える中小土木会社に向けた、「らくらく施工」という選択肢があります。
この記事では、丁張・測量の負担を減らし、現場を楽にする「らくらく施工」について、社長目線で解説します。
この記事の要点(3行でわかります)
- 丁張・測量の負担(時間・人手・手戻り)が現場を圧迫している
- らくらく施工(杭ナビ・快測ナビ)で、1人でも正確に早くできる
- 小規模現場でも始められ、工期短縮・コスト削減につながる
お急ぎの方へ:読む場所を選べます
- 丁張作業の課題を確認したい方 ← 現場の課題(時間・手戻り・属人化)を整理
- らくらく施工とは何かを知りたい方 ← 杭ナビ・快測ナビの基本を理解
- 始め方を知りたい方 ← 3ステップで分かる導入の流れ
- 具体的な導入事例を見たい方 ← 側溝工事での導入前後の比較
- よくある不安を解消したい方 ← 小規模現場でもできる?コストは?を確認
課題と解決策
現場の丁張作業、こんな課題ありませんか?
時間がかかり、人手が要る(人件費・工期への影響)
丁張をかけるのに、朝の1時間を使う。測量は2人がかり。
こうした作業は、昔から当たり前にやってきたことですが、今はその「当たり前」が現場を圧迫していませんか?
人件費は年々上がり、工期は厳しくなる一方。
丁張や測量に時間を取られると、肝心の施工に充てる時間が削られてしまいます。
結果として、残業が増えたり、工期に余裕がなくなったり。
「もう少し効率化できないものか…」と感じている社長さんは、少なくないはずです。
手戻りが発生しやすく、工期とコストがかさむ
「掘削したら、深すぎた…もう一回やり直し」。こんな手戻り、経験ありませんか?
丁張の高さや位置が微妙にズレていたり、職人によって糸の読み方が違ったり。
アナログな管理では、再現性が低くなりがちです。
しかも、施工中に糸が切れたり、木杭がずれたりすることもある。
図面変更があったとき、丁張を全部かけ直すのも大変です。
他業種との干渉で、現場で急遽修正…なんてことも日常茶飯事。
こうした手戻りが積み重なると、工期は延び、人件費はかさむ。
現場からすれば「仕方ない」で済むかもしれませんが、経営者としては見過ごせない損失です。
ベテラン頼み、若手が育ちにくい(属人化)
「この作業は○○さんじゃないとできない」。そんな状況、ありませんか?
それはつまり属人化しているということ。
測量や丁張は、経験と勘がものを言う作業で、
ベテランが休んだり、辞めたりすると、現場が回らなくなる。
若手に教えようにも、「見て覚えろ」では限界があります。
技術継承がうまくいかないまま、ベテランが高齢化していく。
これは、会社の将来にとって大きなリスクです。
実は、その課題「らくらく施工」で解決できるんです
らくらく施工って何?丁張を減らす・なくす施工方法
「らくらく施工」は杭ナビや快測ナビといったICT機材を使って、丁張や測量の作業を効率化する施工方法のことです。
このような、全面的にICTしない施工も「ICT施工」の一種として認められており、「部分ICT施工」と呼ばれたりします。
▶ ICT施工についてもっと詳しくご覧になりたい方は、ICT施工の説明(詳細版)へ
ちなみに、「らくらく施工」は当社の造語です。
いつもの段取りは大きく変えずに、丁張・測量など負担の大きい工程だけをまずICT化し、
少人数でも正確に短時間で進められる“良さ”を体験してもらいたい。
現場の声を起点に、ICT施工に苦手意識がある方にもとっつきやすい入口として名付けました。
この記事では、当社のPRも含みますが、「らくらく施工」のやり方を学べる記事となっています。
この記事を読んで概要をつかめた方は、当社に頼らず自社で実施いただいてもOKですので、ぜひ、らくらく施工を貴社でも取り入れてください。
杭ナビ・快測ナビという道具で、現場が変わる
らくらく施工では、「杭ナビ」と「快測ナビ」という2つの道具を組み合わせて使います。
杭ナビは、位置出しや丁張を一人で簡単にできるシステムです。
従来は2人でやっていた測量・位置出しを、1人でできるようにしてくれます。
タブレットに設計データを表示し、
「ここに杭を打つ」「ここが中心線」とリアルタイムで案内してくれるので、
丁張がなくても正確に位置を出すことができます。
快測ナビは、設計図面をタブレットで見ながら、その場で出来形を確認・記録できるアプリです。
杭ナビで測った位置情報をリアルタイムで表示し、
「設計の底高はここ」「今の掘削深さはここ」と、現場全員が同じ情報を見ながら作業できます。
つまり、杭ナビが「測る」、快測ナビが「見る・記録する」。この2つを組み合わせることで、丁張や測量の負担を大きく減らすことができます。
当社のいう「らくらく施工」には含まれませんが、
快測ナビは、出来形管理や写真記録もこのアプリで行えるので、
もう少し進んだ部分ICT施工として、利用することもできます。
ピンク:このあたりがワクワークの勧める「らくらく施工」に含まれていれば文章を少し変更します。(沖村)
丁張がなくなると、現場はこう変わる
変化①:朝の準備時間が短縮、工期に余裕が生まれる
丁張をかける時間が、ほぼゼロになります。
従来なら朝の1時間を丁張に使っていたところが、杭ナビで位置出しをすれば15〜20分で完了するので、その分、施工に充てる時間が増えます。
1日単位で見れば小さな差ですが、工事全体で見れば工期の短縮につながります。
工期が短くなれば、次の現場に早く入れる。それは、売上の機会を増やすことでもあります。
オレンジ:あっていますか?(沖村)
変化②:2人作業が1人でできる、人件費削減にも
測量や位置出しは、従来「2人1組」が基本でした。でも、杭ナビを使えば、1人で完結できます。
人手不足の今「2人必要な作業が1人でできる」というのは、それだけで大きなメリットです。
単純計算で人件費が半分になるわけではありませんが、限られた人員を他の作業に回せるようになります。
「人が足りなくて現場が回らない」という状況を、少しでも緩和できるのは大きいと言えます。
変化③:若手でも正確に位置出しができる、技術継承が進む
杭ナビは、タブレット画面に「ここです」と表示してくれます。
だから、経験の浅い若手でも、ベテラン並みの精度で位置を出せるようになります。
「○○さんじゃないとできない」という属人化が減り、若手も早く戦力になり、
技術継承のハードルも下がることで、会社全体の技術力の底上げにつながります。
これは、長期的に見れば、会社の競争力を高めることでもあります。
はじめ方とやり方
らくらく施工、どうやって始める?(概要)
ステップ①:まずは情報収集(見学・相談)
いきなり「次の現場で使おう」と決めなくても大丈夫です。
まずは、話を聞いてみる。現場を見学してみる。それだけでも十分です。
「どんな機材なのか」「実際にどう使うのか」を見れば、「うちでもできそうかな」というイメージが湧いてきます。
当社でも、不定期ですが、無料の相談会や見学会を開催しているもあるので、気軽に参加してみてください。
開催などのお知らせは、公式Instagramや当サイトのお知らせから行っていく予定です。(ぜひ、フォローください)
ステップ②:小さい現場で試験導入
「やってみようかな」と思ったら、まずは小さい現場で試してみましょう。
いきなり大きい工事で使うのではなく、側溝工事や小規模擁壁など、リスクの少ない現場で試験的に導入する。
どんな工事と相性がいいかは、[ICT施工、初めてトライするのに適した工種とは(小規模土工)]もぜひご覧ください。
小さく始めて、徐々に慣れていく。それが、失敗しないコツです。
ステップ③:現場が慣れてきたら、他の工事にも展開
1現場を終えれば、現場も機材の操作に慣れてきます。そうしたら、次の工事でも使ってみる。
何現場か経験を重ねていくうちに、「これが普通」という感覚になってきます。
そして、規模の大きい工事があれば、もう少し適用範囲を広げた部分ICT施工に挑戦してみる。らくらく施工は、その土台になります。
らくらく施工、どうやってやる?(実践)
側溝工事での使い方を、工程ごとに解説
例えば、L型側溝の据付工事(延長50m)を想像してください。
らくらく施工では、以下のような流れで作業を進めます。
工程①:基準点の設定と座標登録(杭ナビ)
まず、現場に既知点・基準点を設定します。これは従来の測量と同じです。
杭ナビのタブレットに、この基準点の座標を登録します。
トータルステーション(測量機)を基準点に据え付け、杭ナビと接続。
これで、現場の座標系が確立されます。
所要時間:約10分
工程②:中心線の位置出し(杭ナビ+快測ナビ)
次に、側溝の中心線を位置出しします。
タブレットの快測ナビに、側溝の設計データ(中心線・端部・曲点の座標)を読み込んでおきます。
杭ナビのポールを持って現場を歩くと、タブレット画面に「あと2m前」「あと30cm左」とリアルタイムで表示されます。
画面の指示に従って移動し、「ここです」という位置に杭を打つ。
これを繰り返して、中心線の杭を設置していきます。
丁張をかける必要はありません。杭と画面があれば、位置は正確に出せます。
所要時間:約15分(従来の丁張設置なら1時間)
工程③:掘削・据付時の確認(快測ナビ)
掘削機で掘削する際、快測ナビの画面で「設計の底高」と「現在の掘削深さ」をリアルタイム表示できます。
オペレーターも、監督も、職人も、同じタブレット画面を見れば、
「あと5cm掘ればOK」「ここは設計通り」と、一目で分かります。
側溝を据え付ける際も、快測ナビで位置と高さを確認しながら進められるので、手戻りがありません。
工程④:出来形測定と記録(快測ナビ)
施工が終わったら、快測ナビで出来形測定を行います。
側溝の天端高や位置を測定し、そのデータをその場でタブレットに記録。
写真も一緒に保存できるので、後日の出来形管理資料作成がスムーズです。
所要時間:約5分(従来の出来形測量なら30分)
黄色:時間などあっていますか?(沖村)
初回現場のチェックリスト
初めてらくらく施工を導入する際、何を準備すればいいのか?当日の流れは?チェックリスト形式でまとめます。
事前準備:必要なデータと確認事項
必要なデータ
- 3次元設計データ(座標データ、中心線データなど)
- 発注図面(念のため紙でも持参)
確認事項
- 基準点の座標(発注者から提供、または事前に観測)
- データ形式が杭ナビ・快測ナビに対応しているか(SiTECH 3D、LandXML、DXFなど)
※3次元設計データの作成は、専門知識が無い場合は、外部に依頼するのが一般的です。(徐々に内製化を推奨します。)
当日の持ち物:機材・バッテリー・予備品
機材
- 杭ナビ本体(トータルステーション+自動追尾ユニット)
- ポール(プリズム付き)
- タブレットかスマホ(快測ナビアプリインストール済み)
電源・予備品
- バッテリー(本体用、タブレット用、予備も必須)
- データUSB(設計データ)
- 三脚、巻尺、杭、ペイント
トラブル対策
- 取扱説明書(紙またはPDF)
- サポート担当者の連絡先
現場での流れ:セットアップ→動作確認→施工→片付け
セットアップ、動作確認
- 基準点にトータルステーションを据え付け
- 杭ナビと接続、座標登録
- タブレットに設計データを読み込み
- 動作確認(テスト測定)
施工
杭ナビで位置出し→掘削→据付→快測ナビで確認
片付け
- データを保存
- 機材を清掃、バッテリー充電
初回は、ICT施工に詳しい人に立ち会ってもらうと安心です。(当社の現場サポートもご利用ください。)
よくある不安やトラブルと、まとめ
「うちみたいな小さい会社でもできる?」
「現場が機械に慣れるか心配…」→ 操作は意外とシンプル
「うちの現場、機械が苦手な人も多いんだけど…」という不安、よく聞きます。
でも、杭ナビ・快測ナビの操作は、スマートフォンやタブレットが使える人なら、すぐに慣れます。
画面をタップして、指示に従うだけで複雑な設定は機械が自動でやってくれます。
実際、「最初は難しいかなと思ったけど、2〜3回使ったら普通に操作できるようになった」という声が多く、
現場の年配の方でも、意外とすんなり使えるようになります。
「小規模現場でも使える?」→ むしろ小規模向き
「うちみたいな小規模現場で、ICT施工なんてオーバースペックでは?」と思われるかもしれません。
でも、実はらくらく施工は小規模現場にこそ向いています。
大規模現場と違って、丁張を何十本もかけるわけではありませんし、測量範囲も限られています。
だからこそ、杭ナビ・快測ナビの「手軽さ」「早さ」が際立つと言えます。
側溝工事、小規模擁壁、U字溝敷設など、日常的な工事でこそ、らくらく施工の効果を実感できます。
「コストは?」→ レンタルで始められ、工期短縮で回収可能
「ICT施工は高い」というイメージがあるかもしれません。
でも、らくらく施工で使う杭ナビ・快測ナビは、レンタルで利用できます。
購入する必要はなく、1現場あたり数万円程度でレンタル可能です。
しかも、工期が短縮できれば、その分の人件費削減で十分に回収できます。
実際、先ほどの例のように「投資した分、回収できた」という声は多いです。
また、ICT施工の対象工事であれば、積算基準にICT関連費用が計上されているケースもあるため、発注者がコストを負担してくれる場合もあります
(※ただし、発注者により異なりますので、詳しくは各発注者の積算要領をご確認ください)。
「誰に教わればいい?」→ 希望に合わせて、伴走してもらえる
「機材を借りても、使い方が分からなかったらどうしよう…」という不安もありますよね。
安心してください。らくらく施工を始めるとき、ワクワークにご相談いただければ、
必要に応じ、現場に一緒に立ち会って操作の説明をしてもらうこともできます。
「どのボタンを押せばいいか」「データがうまく表示されないときはどうするか」といった、
現場で起こりがちな疑問を、その場で解決しながら進められるので、現場も安心です。
通常は、1現場だけ立ち合えば、次の現場から使いこなせる会社さまがほとんどなので、
2現場目以降は、杭ナビ・快測ナビの操作は自分たちでできるようになっているはずです。
もちろん、必要に応じて、2現場目以降もサポートいたします。
よくあるトラブルと対処法
初めて使う際、こんなトラブルが起こることがあります。でも、対処法を知っておけば慌てずにすみます。
データが表示されない
原因
- データ形式が合っていない
- ファイルの読み込みパスが間違っている
解決策
- データ形式を再確認
- タブレットの設定で、正しいフォルダを指定
- 事前にテストデータで動作確認しておく
位置がズレる
原因
- 基準点の座標が間違っている
- トータルステーションの据え付けがズレている
解決策
- 基準点の座標を再確認
- トータルステーションを据え直し、キャリブレーション(校正)を実施
- 既知の2点間距離を測定し、精度を確認
バッテリーが切れた
原因
- バッテリーの充電不足
- 長時間使用でバッテリー消耗
解決策
- 前日に必ずフル充電
- 予備バッテリーを2個以上持参
- 車で充電できる環境を確保
トラブルの多くは、事前準備と予備の用意で防げます。
まとめ
現場の負担を減らすことが、会社の未来を作る
丁張や測量の負担を減らすために、「らくらく施工」という選択肢があります。
小さく始めて、徐々に広げていく。
らくらく施工なら、
現場が楽になり、工期も短縮できるし、人件費も削減できる。
若手も育ちやすくなるし、何より、会社の競争力が高まります。
「人が足りない」「ベテランに頼りきり」「若手が育たない」。
そんな悩みを抱えているなら、まずは一度、らくらく施工について話を聞いてみませんか?
現場の負担を減らすことが、会社の未来を作る。その第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
無料相談・現場見学会のご案内
らくらく施工に興味を持たれた方、「うちの現場でも使えるかな?」と気になった方は、ぜひお気軽にご相談ください。
現場の状況をお聞きしながら、最適な始め方をご提案します。
実際に機材を見てみたい方には、現場見学会もご案内できます。
関連記事
- 前の記事(【初心者向け】ICT施工とは?仕組みと導入のハードルを下げる方法)
- 次の記事(ICT施工の始め方|部分ICT施工で段階的にチャレンジ)
- サービスについて見る(ICT施工サポート)