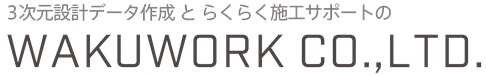【初心者向け】ICT施工とは?仕組みと導入のハードルを下げる方法
「ICT施工って何?」と思っている方へ
「ICT施工って何?」「うちみたいな小さい会社には関係ない話じゃないの?」
そんな風に思っていませんか?
確かに、ICT施工と聞くと
「大手ゼネコンの話」「最新機械が必要」「お金がかかりそう」というイメージを持つ方が多いかもしれません。
でも実は、中小の土木会社でも、一部だけ取り入れるだけで工期短縮や品質向上が期待できる施工方法なんです。
この記事では、ICT施工の基本から、中小企業でも無理なく始められる方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
ICT施工とは? 3分でわかる基本の仕組み
ICT施工の定義
ICT施工とは、Information and Communication Technology(情報通信技術)を活用した施工方法のことです。
国土交通省が推進する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」の一環として、2016年から本格導入されました。
簡単に言えば、測量から設計、施工、検査、納品まで、すべての工程を3次元データ(3Dデータ)で管理するやり方です。
従来の「紙の図面を見ながら、人の手と目で測る」施工から、「デジタルデータを使って、機械が支援してくれる」施工へと変わります。
「情報化施工」との違いは?
「情報化施工」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、ICT施工と情報化施工はほぼ同じ意味です。
- 情報化施工:2008年頃から使われていた呼び名(古い呼び方)
- ICT施工:2016年のi-Construction開始後の呼び名(新しい呼び方)
現在は「ICT施工」が公式な呼称として使われていますので、この記事でも「ICT施工」で統一します。
従来の施工との3つの違い
| 項目 | 従来の施工 | ICT施工 |
|---|---|---|
| 測量 | 2次元(平面図) | 3次元(立体データ) |
| 図面 | 紙の図面 | デジタルデータ (3次元設計データ) |
| 施工 | 手動操作 (人の感覚による) |
機械支援 (MC/MGなどで補助) |
① 測量が2次元→3次元に
従来はレベルやトランシットを使って1点ずつ測っていましたが、
ICT施工ではドローンやGNSS測量機、レーザースキャナを使って地形を一気に3D化します。
② 紙の図面→デジタルデータに
紙の図面ではなく、3次元設計データを作成し、ICT建機等に読み込ませて使います。
③ 手動操作→機械支援に
ブルドーザーやバックホウなどのICT建機に設計データを入れると、
「あと何cm掘ればいいか」を機械が教えてくれるので、ベテランでなくても精度の高い施工ができます。
MC(マシンコントロール):機械が自動で刃先を制御
MG(マシンガイダンス):モニターに「あと○cm」と表示し、オペレーターが操作
ICT施工の5つの工程(i-Constructionの流れ)
ICT施工は以下の5つの工程で進みます。
- 3次元起工測量
- 3次元設計データ作成
- ICT建機による施工(MC/MG)
- 3次元出来形管理
- データの納品(電子納品)
① 3次元起工測量
現場の地形を3次元で測る工程です。
ドローンやGNSS測量機、地上レーザースキャナなどを使用します。
→ 精度の高い地形把握が可能になります。
② 3次元設計データ作成
測量データをもとに完成形の3Dモデルを作る工程です。
専用ソフト(SiTECH 3D、Civil 3D、LandXML対応CADなど)を使用します。
③ ICT建機による施工(MC/MG)
設計データをICT建機に読み込ませて施工します。
オペレーターの感覚ではなく、データに基づく施工が可能になります。
④ 3次元出来形管理
完成後の地形を3D測量し、設計データと比較します。
「何十点も測る」従来の手作業が不要になり、短時間で確認が完了します。
⑤ データの納品(電子納品)
測量・設計・出来形の3Dデータを電子的に納品します。
紙図面が最小限になり、情報の一元管理が可能です。
ICT施工のメリット・デメリット
メリット①:工期短縮・生産性向上
3次元データをもとに機械が自動で動作を補助するため、施工スピードが大幅に上がります。
従来、5日かかっていた整地や盛土作業が3日で済んだり、精度が安定するため再施工(手戻り)も減少することで、工期短縮に貢献します。
現場例:MG付きバックホウを使った掘削工事で、若手オペレーターでも手戻りなく完了。ベテラン不在でも、2日早く仕上げられた。
メリット②:品質向上・手戻り削減
ICT施工では、設計と実測が同じ基準(3次元データ)で比較されるため、「掘りすぎ・盛りすぎ」が起きにくくなります。
そのため、材料ロスが減り、品質のばらつきも抑えられます。
メリット③:安全性・技術継承
ICT建機はデータに基づいて操作補助を行うため、危険エリアでの作業や手元作業の負担を軽減できます。
また、ベテランの“勘”に頼らず、データで判断する施工なので、若手への技術継承もスムーズになります。
デメリット①:初期コスト・学習コスト
ICT建機や3次元測量機器は高価です。
レンタルでも通常の建機より1.5〜2倍程度高くなる場合があります。
また、データ作成には専用ソフトとスキルが必要です。
ただし、測量やデータ作成を外注すれば、初期投資を最小限に抑えることができます。
また、発注条件によっては、工事費に上乗せすることも可能です。
デメリット②:すべての現場で使えるわけではない
以下のような現場では、導入効果が薄い場合もあります。
- 狭小地(ICT建機が回転できない)
- 短工期(データ作成に時間が取れない)
- 地中障害物が多い現場(データと実態が合いにくい)
そのため、適用判断と現場選定が重要です。
デメリット③:操作やデータ処理の慣れが必要
測量データ処理や専門ソフトの扱い、新しい装置の現地での使い方など、最初は専門知識が必要です。
ただし、
現地での操作は、1〜2回経験すれば理解できることがほとんどですし、
データに関しては、外注などで乗り切ることが可能です。
ピンク:言い切ってOK?(沖村)
全面ICT施工(フルICT施工)と部分ICT施工の違い
ICT施工には、実施範囲によって大きく分けて 全面ICT と 部分ICT の2種類があります。
全面ICT施工(フルICT施工)とは
5つの工程すべてを3次元で実施する方式です。
主に国交省や自治体が「ICT活用工事」として指定した現場が対象です。
対象工事
- 国交省・県などの「ICT活用工事」指定現場
- 要件:3次元測量・3次元設計データ・ICT建機施工・出来形管理・電子納品の全実施
メリット
- 工事成績評定で加点されることがある(※自治体による)
- 大幅な工期短縮・精度向上が可能
デメリット
- 機材・ソフト・人材の初期投資が大きい
- 小規模工事ではオーバースペックになりやすい
部分ICT施工とは
全面ICT施工の5工程のうち、一部だけを3次元化する方法です。
茨城県では「チャレンジいばらきⅠ・Ⅱ型」など、独自発注方式にも活用されています。
実際の現場では、次のようなパターンが多く見られます。
代表的な部分ICT施工例 内容
- 起工測量+出来形管理を3D化 現況と完成形の把握を効率化。ICT建機は使わない。
- 杭ナビ・快測ナビによる施工支援 3D設計データを活用して位置出し・丁張を省力化。
- 3D設計データを使いMG施工 建機は通常タイプ、表示支援で施工精度を向上。
ポイント
部分ICT施工は「自由に好きな工程を選ぶ」というより、自社の規模・発注条件・目的に応じて段階的に導入するイメージです。
比較で見る違い
| 項目 | 全面ICT施工 (フルICT施工) |
部分ICT施工 |
|---|---|---|
| 対象工事 | 国交省や都道府県発注工事など | 地方自治体指定工事など |
| 実施工程 | すべて | 一部 (測量のみ、施工のみ、出来形のみ など) |
| 必要機材 | ICT建機+測量機器一式 | 必要部分のみ |
| 費用感 | 高い(数百万円〜) | 低い(数十万円〜) |
| 導入難易度 | 高い 専任技術者がいたほうが良い。 ただし一部外注でも可 |
中〜低 (外部支援で可) |
| 効果 | 最大 (30%短縮など) |
中程度 (10〜20%短縮) |
| 適した工事規模 | 中規模~大規模 | 小規模~中規模 |
黄色:もっと効果があるイメージですがどの程度ですか?(沖村)
「部分ICT施工」を後押しする“らくらく施工”
中小企業が最初に取り組みやすいのが、
「らくらく施工」=杭ナビや快測ナビを使った部分ICT施工です。
紙の図面を3次元データに変換し、
杭ナビで位置出し・快測ナビで出来形確認を行うことで、
人手不足でも精度高く・短時間で施工できます。
例:らくらく施工で変わる現場の一日
| 従来 | らくらく施工 |
|---|---|
| 丁張り位置を手測量・木杭打ち | 杭ナビが自動で誘導。木杭・水糸が不要。 |
| 出来形確認を巻き尺で複数点測定 | 快測ナビで3Dデータを一括比較。手戻りゼロ。 |
| 測量後の図面修正に時間がかかる | 現場でリアルタイムに補正・共有可能。 |
用語について:
「らくらく施工」は当社の造語です。
いつもの段取りは大きく変えずに、丁張・測量など負担の大きい工程だけをまずICT化し、
少人数でも正確に短時間で進められる“良さ”を体験してもらいたい。
現場の声を起点に、ICT施工に苦手意識がある方にもとっつきやすい入口として名付けました。詳しくは らくらく施工とは(詳細版)
外部サポートを活用して“無理なく導入”
「3次元測量なんてできない」「データ作成のソフトがない」
そんなときは、外注先を探すことも検討ください。
- 測量や設計データ作成だけ外注
- 初回のみ現地OJT支援を受ける
- 困った時だけスポットで相談
こうした伴走型支援を活用すれば、初めてでも安心してICT施工を導入できます。
ICT施工は「いきなり全部」じゃなくてOK
ICT施工は、大手だけの話ではありません。
部分ICT施工+外部サポート(例:当社のICT施工サポート)を使えば、
中小企業でも現実的に始められます。
- 測量〜施工〜出来形のどこからでも始められる
- 3次元化は「必要な部分から」で十分
- 一度導入すれば、次の現場が格段にスムーズに
一言まとめ
ICT施工の目的は「フル3D化」ではなく、“自社に合った省力化・見える化”を実現すること。まずは一部から、小さく始めてOKです。
関連記事
- 次の記事(小規模現場の丁張・測量の負担を減らす、らくらく施工という選択)
- サービスについて見る(ICT施工サポート)